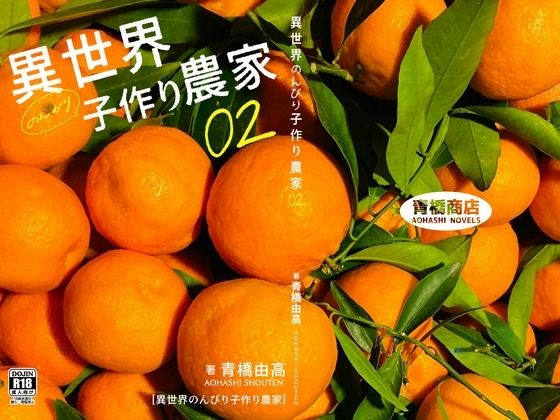童貞は母に懇願する
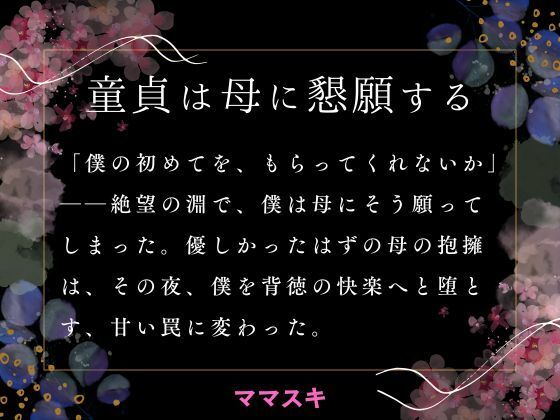
僕は、童貞であることに深く悩んでいた。周りの友人たちが当たり前のように恋愛を経験していく中で、自分だけが取り残されていく焦りと劣等感に、僕は押し潰されそうになっていた。
ある夜、その苦しみに耐えきれず、僕は自室で泣き崩れてしまった。そこへ心配してやってきた母さんに、僕は、言ってはならないと分かっていながら、心の叫びをぶつけてしまう。
「誰でもいい、母さんでもいいから、僕の初めての相手になってほしい」と。
その絶望的な僕の願いを聞いた母さんの母性本能は、どこか歪んだ形で暴走を始めた。
「あなたの苦しみは、ママが全部受け止めてあげる」
総字数 約4000字
―――
(試し読み1)
僕は、母親の腰に、まるで子供が甘えるようにしがみついた。そして、これまで誰にも言えなかった、心の奥底に溜め込んでいた醜い感情を吐き出した。「僕……童貞なんだ……っ」。その優しさが、僕をさらに惨めにさせ、あり得ない、禁断の言葉を、僕の口から滑り出させた。「もう、嫌なんだ……っ。誰でもいいから……僕の、初めての相手になってほしい……っ」。それは、あまりにも身勝手で、背徳的な願いだった。
(試し読み2)
母親は、僕の体をゆっくりと自分から離させると、涙でぐしゃぐしゃになった僕の顔を、その両手で包み込んだ。そして、僕の瞳をまっすぐに見つめて、こう言った。「ママがいるから。あなたのその苦しみ、ママが、全部受け止めてあげる」。その瞳は、もはや単なる母性のものではなかった。僕の絶望的な告白が、彼女の中にあった、何か特別な感情のスイッチを入れてしまったのだ。
(試し読み3)
やがて、僕の中心で、信じられないほど温かく、湿ったものがうごめいた。それが母さんの口だと気づいた時、僕の頭は、本当にどうにかなってしまいそうだった。僕にできることは、ただシーツを強く握りしめ、母さんが与えてくれる、あまりにも背徳的な快感の波に、なすすべもなく身を任せることだけだった。