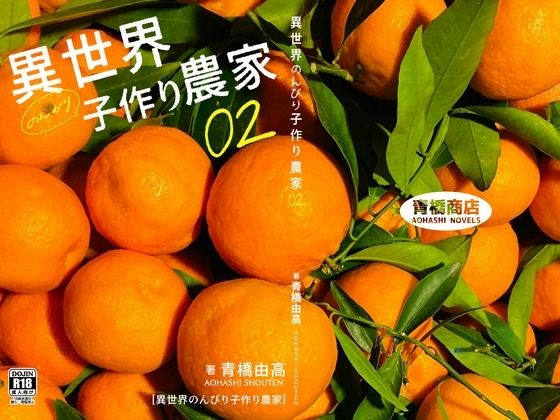童貞は母と遊ぶ
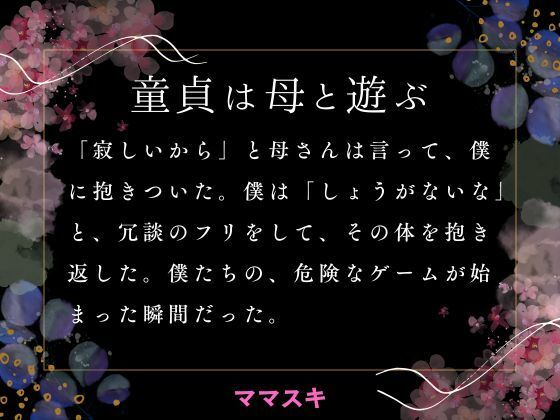
父さんの単身赴任で、母さんと二人きりになった家は、どこか寂しかった。そんな寂しさを紛らわせるように、母さんは、僕に冗談で抱きついたり、キスをしたりするようになったんだ。童貞であることに焦っていた僕は、それを「チャンス」だと捉え、冗談のフリをしながら、母さんとのスキンシップをエスカレートさせていった。
「ごっこ遊び」のはずだった僕たちの関係は、日に日に境界線が曖昧になり、互いの体に、本気の欲望を抱くようになっていく。
総字数 約3000字
―――
(試し読み1)
映画が終わると、母さんは、「寂しくなっちゃった」と、子供みたいに言って、ぎゅっと、僕の腕に抱きついてきた。そして、僕の頬に、チュッ、と、わざとらしい音を立てて、キスをした。その、あまりにも無邪気な、冗談交じりのスキンシップ。しかし、僕の心は、全く別のことを考えていた。―――これは、チャンスだ。母さんの孤独につけ込む、絶好の機会だ。僕は、笑いながら、その体を、そっと抱き返した。
(試し読み2)
冗談として始まったスキンシップは、日に日にエスカレートしていった。ソファで隣に座れば、肩が触れ合う。テレビを見ていると、僕の膝に、母さんが頭を乗せてくる。そして、母さんの方も、明らかに変化していた。僕を見る、その眼差し。その全てが、熱を帯びてきている。それはもう、息子に向けるものではなく、一人の「男」に向ける、甘く、危険な色をしていた。
(試し読み3)
「あなたのこと、食べちゃいたいくらい、可愛いわ」。その言葉が、最後の合図だった。僕は、母さんを、強く抱きしめた。母さんの、震える指が、僕のパジャマのボタンを、一つ、また一つと、外していく。冗談のフリをした、長い、長い前戯は終わったのだ。僕たちは、まるで飢えた獣のように、互いの体を、貪り合った。僕の、惨めだった童貞は、母さんの、孤独な体の中で、その終わりを告げた。