ジムトレーナーに寝取られた母
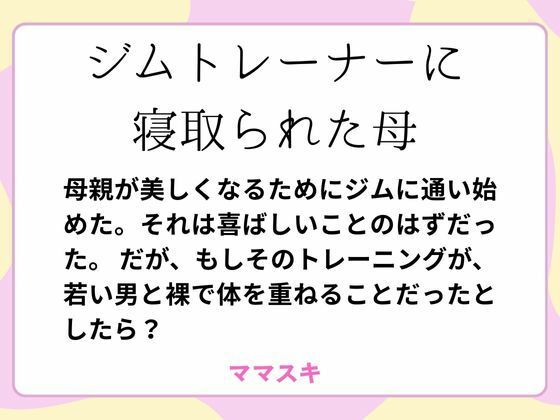
義孝は、最近スポーツジムに通い始めた母親が、特定の若いトレーナー・涼太の話ばかりするのに、かすかな違和感を覚えていた。ある夜、母親が「残業」と嘘をついて外出したことを察した義孝は、いてもたってもいられずジムへと向かう。閉館したジムに忍び込み、彼がトレーニングルームのドアの隙間から見たのは、ベンチプレス台の上で涼太と体を重ね、快感に溺れる母の衝撃的な姿だった。「健全な場所」で行われる不健全な行為に深い喪失感を覚えながらも、そのあまりに肉体的な光景に背徳的な興奮を感じてしまう義孝。彼の日常は、静かに、そして決定的に変質していく。
総字数 約4000字
―――
(試し読み1)
義孝が何気なく母親の部屋に入ると、ドレッサーの上に、若々しく笑う母親と父親のツーショット写真が飾られていた。その時だった。写真立てのすぐ横に、無造作に畳んで置かれたタオルが彼の目に留まる。白地に、青い文字でスポーツジムのロゴが入っている。バラバラだったパズルのピースが、頭の中で音を立ててはまっていく。「残業」という嘘。楽しそうに話していた「涼太君」。そして、父の写真の隣に置かれたジムのタオル。母さんは、父さんを裏切っているのではないか。
(試し読み2)
義孝は息を殺し、建物の裏手にある通用口の隙間から中へと忍び込んだ。ジムの中は、非常灯だけが点灯し、薄暗い。汗と消毒液の混じった独特の匂いが鼻をついた。一番奥にあるトレーニングルームのドアの下から、うっすらと光が漏れているのが見えた。そして、微かに聞こえる話し声。母親の声と、若い男の声だ。義孝の心臓が、肋骨を突き破るほど激しく高鳴る。彼は壁に背中を押し付け、ドアのガラス窓にそっと顔を近づけた。
(試し読み3)
涼太の若くたくましい指が、母親の肌の上を滑り始めた。腹筋の縦のラインを確かめるように、ゆっくりと。「んっ……やめて……」母親は身を捩らせて抵抗しようとするが、涼太は力強くその体を押さえつける。彼の指は、まるで体のツボを知り尽くしているかのように、敏感な場所を探り当てていく。冷たいベンチプレスのレザーと、涼太の熱い指先。その刺激に、母親の体から次第に力が抜けていく。抵抗の言葉は、いつしか意味をなさない、甘い喘ぎ声に変わっていた。



























